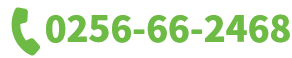ペースメーカーで障害年金はもらえるの?社労士が解説!【新潟で障害年金にお悩みの方へ】
最終更新日 25-08-13
ペースメーカーと障害年金の基礎知識
心臓の病気により、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着された方、あるいはこれから手術を検討されている方もいらっしゃるでしょう。これらの機器は命を守るために不可欠ですが、装着後も体調管理や日常生活、仕事に様々な制約を受けることがあります。
そんな時に、あなたの生活を経済的に支える制度が「障害年金」です。ここでは、まずペースメーカーやICDの基本的な情報と、障害年金制度の概要について解説します。
ペースメーカー・ICDとは?
ペースメーカーやICDは不整脈を正常な状態に戻すために体内に植え込む医療機器です。
- ペースメーカー:
洞不全症候群や房室ブロックなど、脈が遅くなるタイプの不整脈に対して、電気刺激を送って心臓の拍動を補い、適切な脈拍を保つ役割をします。 - ICD(植込み型除細動器):
心室細動や心室頻拍など、突然死につながる危険な頻脈性不整脈を自動的に感知して電気ショックを与えることにより心臓の拍動を正常に戻す救命装置です。
ペースメーカー等を装着することで症状が安定し、日常生活を送れるようになりますが、制約が伴います。
障害年金の概要と目的
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
ペースメーカーやICDを装着した方も、障害年金の対象となります。
安定した収入が継続的に得られることは、ご本人の経済的な安心だけでなく、精神的な安定にも繋がり、治療への専念や、無理のない働き方への移行を支える重要な役割を果たします。
ペースメーカー・ICDにおける障害年金のポイント
ペースメーカーやICDで障害年金を申請する場合、最も重要なポイントは「どの種類の機器を装着したか」ということです。装着した機器によって、認定される障害等級が原則として決まっています。
- ペースメーカー、CRTを装着した場合 → 原則として「障害等級3級」
- ICD、CRT-Dを装着した場合 → 原則として「障害等級2級」
このように、機器の種類によって等級が異なるため、ご自身がどの機器を装着しているのかをまずは確認しましょう。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、定められたいくつかの要件をすべて満たす必要があります。ここでは、障害の程度を示す「障害等級」や、申請に必要な「初診日」など、具体的な受給要件について解説します。
障害等級の説明(1級、2級、3級)
障害年金は、障害の状態に応じて1級、2級、3級の等級に分けられます。心疾患における等級の目安は以下の通りです。
- 1級: 身の回りのことがほとんどできず、常時介助が必要な状態。
- 2級: 家庭内の軽い活動はできても、それ以上の活動はできない状態。
ICDを装着した場合に該当
- 3級(厚生年金のみ): 労働に著しい制限が必要な状態。
ペースメーカーを装着した場合に該当
※ 障害厚生年金の加入者で、3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給される「障害手当金」の制度もあります。
障害認定日の特例について
障害認定日は初診日から1年6か月経過後となりますが、「初診日から1年6か月以内にペースメーカー等を装着した場合は、その装着した日を障害認定日とする」と定められています。
これにより、初診日から1年6か月を待たずに、手術を受けた日が障害認定日となります。もし請求が遅れても、この日から5年以内であれば遡って受給することができます。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガ(動悸、息切れ、心電図異常など)で初めて医師の診察を受けていることが必要です。この日を「初診日」といいます。
障害年金3級の場合は、初診日が厚生年金の加入期間である必要があります。
②保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが必要です。
この要件を満たせない場合でも、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよい、という特例があります。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
原則として、初診日から1年6か月が経過した日が「障害認定日」となりますが、ペースメーカーやICDには特例があります。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。
具体的な申請手続きの流れ
障害年金の申請は、一般的に以下の流れで進めます。
- 年金事務所への相談: まずはお近くの年金事務所や年金相談センターに相談し、必要な書類や手続きの概要を確認します。
- 初診日の証明: 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。カルテが破棄されているなど証明が難しい場合は、専門家である社労士に相談することをお勧めします。
- 診断書の作成依頼: 現在通院している医療機関に、障害年金用の診断書(循環器疾患の障害用)の作成を依頼します。装着した機器の種類や装着日を正確に記載してもらうことが重要です。
- 申立書の作成: 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。発症から装着に至るまでの経緯や、装着後の日常生活・就労における支障を、ご自身の言葉で伝えるための重要な書類です。
- 書類の提出: 揃えた書類を年金事務所または市区町村役場の窓口に提出します。
障害年金の金額について
障害年金を受給できるとなった場合、実際にいくらくらい受け取れるのかは、最も気になるところでしょう。ここでは、ペースメーカーやICDで受給する場合の支給額の目安や注意点について解説します。
ペースメーカー・ICDにおける支給の目安額
障害年金の額は、年金の種類(基礎・厚生)と障害等級によって決まります。以下は令和7年度の年額です。
- 障害基礎年金
- 1級: 1,039,625 円 +子の加算
- 2級: 831,700 円+ 子の加算
※子の加算:18歳年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されます。第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円です。
- 障害厚生年金
- 1級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額
- 2級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
- 3級: (報酬比例の年金額) ※最低保障額 623,800円
※報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬額(給与)によって異なります。
※配偶者の加給年金額:生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(年額239,300円)。
支給額が「もらえない」ケースとは?
申請しても障害年金が受給できない(不支給となる)ケースには、主に以下の理由が挙げられます。
- ペースメーカー(3級)で、初診日に国民年金に加入していた場合: 障害等級3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に自営業や無職などで国民年金に加入していた場合は、支給対象外となります。
- 保険料納付要件を満たさない場合。
- 初診日を特定できない、または証明できない場合。
更新が必要な「有期認定」について
ペースメーカーやICDは、数年ごとに診断書の提出が必要な「有期認定」となるのが一般的です。
これは、内蔵されている電池に寿命があり、数年から10年程度で交換手術が必要になるためです。そのため、更新のタイミングで障害状態を再確認することとされています。更新時の診断書の内容によっては、等級が変更されたり、支給が停止されたりする可能性もありますので、定期的に受診を受け、ご自身の状態を医師に伝えておくことが大切です。
障害年金の申請時のポイント
障害年金の申請は、書類審査です。提出する書類の完成度が、結果を大きく左右します。
有効な診断書の書き方とは
診断書は、障害等級を決定づける最も重要な書類です。ペースメーカー・ICDの場合、診断書の様式は「循環器疾患の障害用」を使用します。医師に依頼する際は、以下の点を正確に記載してもらうよう、しっかり伝えましょう。
- 傷病名: 「洞不全症候群」「心室細動」など、原因となった傷病名。
- 装着した機器の種類・型式(型番): 「ペースメーカー」「ICD」などの種類と、具体的な製品名や型番。
- 装着年月日: 機器を植え込んだ年月日。障害認定日の特例に関わるため極めて重要です。
診断書を受け取ったら、ご自身でもこれらの情報が正しく記載されているか、確認しましょう。
必要な証明書と書類一覧
障害年金の申請には、主に以下の書類が必要です。
- 医師に作成してもらう書類
- 診断書
- 受診状況等証明書(初診の病院と診断書作成の病院が違う場合)
- 自身で用意する書類
- 年金請求書
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍謄本、住民票など(配偶者・子供の確認のため)
- 預金通帳のコピー
- 年金手帳・マイナンバーカードなど
これらの書類に不備があると、返戻されたり審査が遅れたりする原因になります。
参照:厚生労働省 障害基礎年金を受けられるとき
参照:厚生労働省 障害厚生年金を受けられるとき
参照:厚生労働省 障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類
申立書とその提出のタイミング
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書では伝えきれないあなたの状況を伝えるための大切な書類です。
書き方のポイント
- 発症から現在までの経過を時系列で分かりやすく記述します。
- 日常生活で不便なこと(動悸や息切れの頻度、疲れやすさ、電磁波を避けるための注意など)を具体的に書きます。
- 仕事で困っていることや、職場から受けている配慮(残業の免除、休憩時間の確保など)を具体的に書きましょう。
受給申請後の流れと注意点
無事に書類を提出した後も、結果が分かるまでは落ち着かない日々が続くかもしれません。申請後の流れを把握しておきましょう。
申請後の審査期間とは
障害年金の申請書類を提出してから、結果が通知されるまでの審査期間は、障害基礎年金でおおむね3か月程、障害厚生年金では3か月半程かかる傾向があります。
審査結果は、「年金証書(支給決定の場合)」または「不支給決定通知書」「却下通知書」といった形で郵送されてきます。支給が決定した場合は、年金証書が届いてから約1〜2か月後に初回の年金が振り込まれます。
無料相談受付中
障害年金の申請、特に初診日の特定や書類作成は複雑で、専門的な知識が求められます。社会保険労務士(社労士)は、障害年金の専門家としてあなたの申請を力強くサポートします。
以下のような状況であれば、当事務所の無料相談をご検討ください。
- 手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない
- 初診日の証明が難しい
- 病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない
- 仕事が忙しく、申請準備の時間が取れない
オンラインや実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。
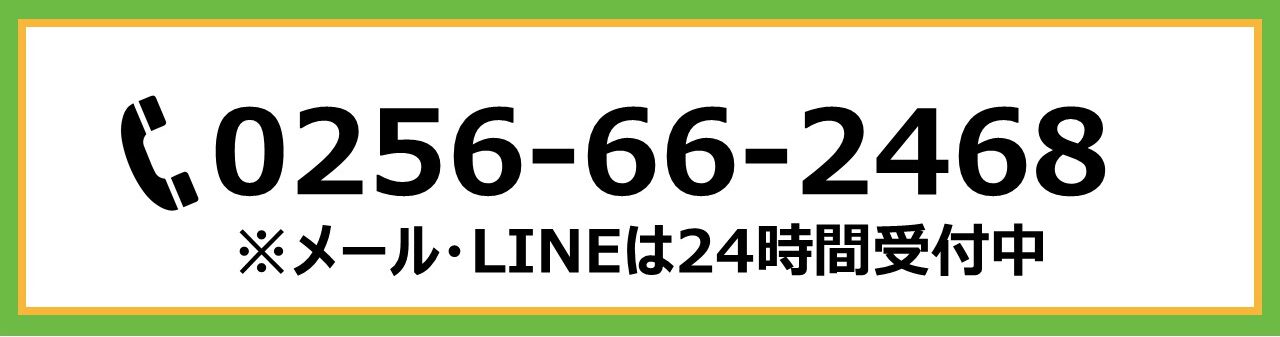
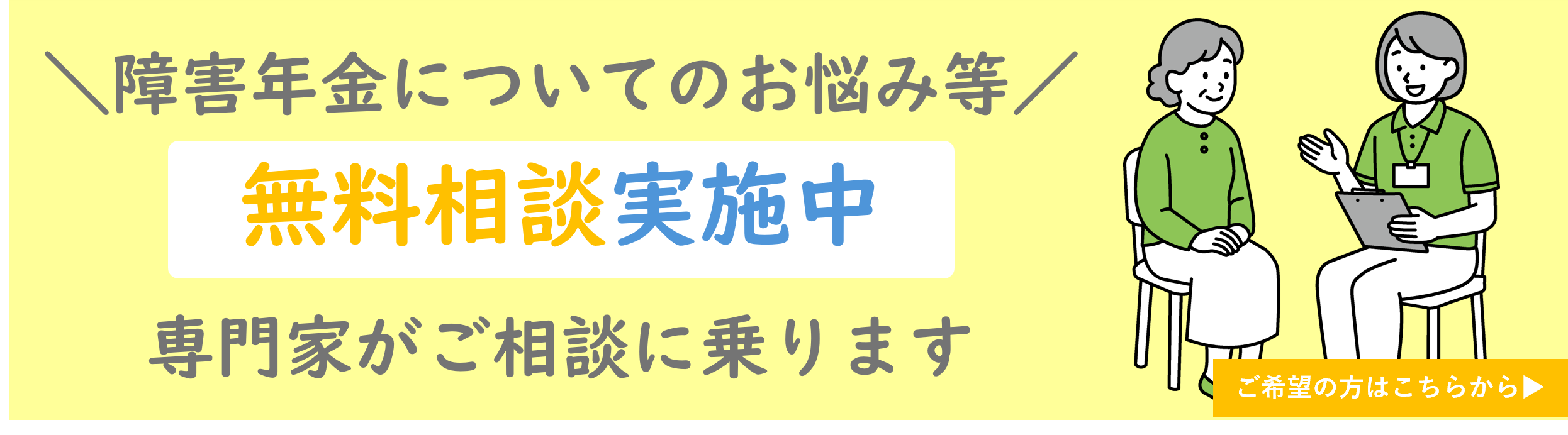
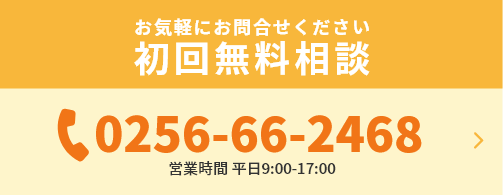
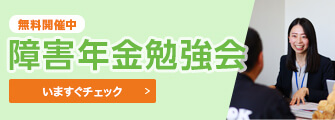
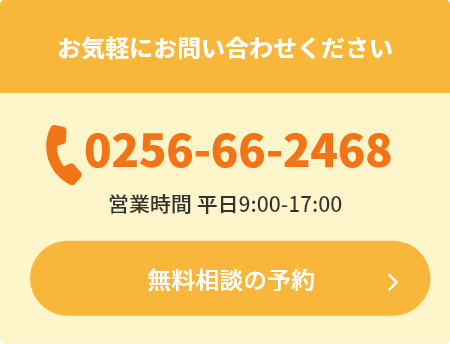
 初めての方へ
初めての方へ