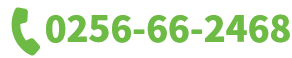障害年金は確定申告が必要?課税・非課税の違いや申告が必要なケースを社労士が解説【新潟で障害年金にお困りの方へ】
最終更新日 25-09-14
障害年金と確定申告について
「障害年金をもらい始めたけれど、確定申告は必要なのだろうか?」「『年金』と名前がつくから、税金がかかるのではないか…」
もしかすると、このように考えて不安に思われたり、どうすれば良いか分からず悩んでしまっている方はいらっしゃいませんか?
毎年、確定申告の時期になると、障害年金を受給されている方から多くのご相談をいただきます。多くの方が、障害年金と税金の関係について誤解されていたり、複雑な制度に戸惑われたりしています。
この記事では、障害年金と確定申告の基本的な関係から、確定申告が必要になる具体的なケース、そして申告によって税金が戻ってくる可能性まで、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。あなたの不安を解消し、正しく制度を理解するためのお手伝いができれば幸いです。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって法律で定められた障害の状態になり、日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的な年金です。現役世代の方も対象となる、生活を支えるための大切な経済的基盤です。障害基礎年金、障害厚生年金の2種類があります。
確定申告の基本知識
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、国(税務署)に申告・納税する手続きのことです。会社員の方は通常、会社が年末調整で手続きを代行してくれますが、個人事業主の方や、給与以外に一定の所得がある方などは、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要な理由
確定申告は、単に税金を納めるためだけの手続きではありません。納めすぎた税金を取り戻す「還付申告」という側面もあります。医療費がたくさんかかった場合(医療費控除)や、特定の条件に当てはまる場合(障害者控除など)に、確定申告をすることで、払いすぎた税金が手元に戻ってくることがあるのです。
障害年金の税務上の取り扱い
障害年金と税金の関係で、まず最も知っていただきたい重要なポイントがあります。それは、障害年金は非課税であるということです。
課税と非課税の違い
公的年金の中には、老齢年金のように所得税の課税対象となるもの(課税)と、障害年金や遺族年金のように課税されないもの(非課税)があります。
- 課税される年金: 老齢基礎年金、老齢厚生年金など
- 非課税の年金: 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族年金など
法律(所得税法第九条)で、障害年金は所得税がかからないと定められています。したがって、あなたが受け取っている所得が障害年金のみである場合、所得税はかからず、確定申告の義務もありません。
「働いていないから確定申告は関係ない」のではなく、「障害年金はそもそも税金の計算に含めない」と覚えておきましょう。
障害者控除の適用について
障害年金を受給している、または障害者手帳をお持ちの方は、確定申告や勤務先の年末調整で「障害者控除」という所得控除を受けることができます。これは、納税者自身や扶養親族が障害者である場合に、所得から一定の金額を差し引くことができる制度で、結果的に所得税や住民税の負担が軽くなります。
- 障害者控除: 27万円
- 特別障害者控除: 40万円
- 同居特別障害者控除: 75万円
この控除を受けるために、確定申告が必要になる場合があります。
参考:国税庁.No.1160 障害者控除
税務署の手続きと提出書類
障害者控除を受けるためには、確定申告書や年末調整の書類にある「障害者控除」の欄に必要事項を記入します。その際、障害の状況を証明するために、障害者手帳の写しや、医師の診断書などの提出を求められることがあります。
確定申告が必要なケース
「障害年金は非課税」ですが、中には確定申告が必要になる方や、した方が得になる方がいらっしゃいます。どのようなケースが当てはまるのか、具体的に見ていきましょう。
受給者の状況別:独立と同居
確定申告が必要かどうかは、障害年金以外の所得があるかどうかで決まります。
確定申告が不要なケース
- 収入が障害年金のみの方
確定申告が必要になる可能性が高いケース
- 障害年金のほかに、給与所得や事業所得、不動産所得など、年間20万円を超える所得がある方
- アルバイトやパートをしていて、勤務先で年末調整が行われていない方
「働いているから障害年金がもらえない」というのも誤解ですが、「働いている場合は確定申告が必要になることがある」と覚えておきましょう。
扶養家族がいる場合の影響
あなたがご家族の扶養に入っている場合、あなたの所得が一定額以下である必要があります。このとき、非課税である障害年金は、扶養を判定するための所得には含まれません。
逆に、あなたが配偶者や親族を扶養している場合、確定申告で配偶者控除や扶養控除を申請することで、あなたの税金の負担が軽くなります。
障害年金の金額と控除額
障害年金の金額がいくらであっても、それが非課税であることに変わりはありません。しかし、給与所得など他の所得がある場合、その所得の金額から障害者控除などの各種控除を差し引いて税額を計算します。この計算のために確定申告が必要となります。
確定申告のやり方
もし確定申告が必要になった場合でも、手順を理解すれば過度に恐れる必要はありません。
必要な書類と情報
確定申告には、主に以下の書類や情報が必要になります。
- 確定申告書: 税務署や国税庁のウェブサイトから入手できます。
- 源泉徴収票: 給与所得がある場合、勤務先から発行されます。
- 障害者手帳や年金証書など: 障害者控除を受ける場合に障害の事実を証明するものです。
- 各種控除証明書: 生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける場合に必要です。
- 医療費の領収書: 医療費控除を受ける場合に必要です。
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
確定申告書の記入方法
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで、自動的に税額が計算され、申告書を作成することができます。特に、障害者控除の適用を忘れないように注意しましょう。
年末調整との違い
会社員やパートの方は、通常12月に勤務先で「年末調整」を行います。これは会社が個人の代わりに所得税の計算をしてくれる手続きです。
年末調整で障害者控除や扶養控除の申告を済ませていれば、基本的には確定申告は不要です。
ただし、医療費控除を受けたい場合や、年末調整で申告し忘れた控除がある場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告しないとどうなるか?
確定申告について、「面倒だから…」と手続きをしないと、損をしてしまったり、思わぬペナルティが発生したりする可能性があります。
申告しないリスク
給与所得など、申告すべき所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課される可能性があります。
税金が戻る可能性
一方で、より多くの方に関係するのが「申告しないことによる損」です。
例えば、以下のようなケースでは、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
- 給与から所得税が天引きされている(源泉徴収されている)が、年末調整で障害者控除の申告をしていなかった場合
- 年間の医療費が10万円を超え、医療費控除を受けられる場合
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
心当たりがある方は、ぜひ一度、確定申告を検討してみてください。還付申告は、過去5年分さかのぼって行うことができます。
次年度以降の影響
確定申告の内容は、翌年度の住民税の計算にも影響します。正しく申告をすることで、翌年からの住民税が安くなるというメリットもあります。
特例と制度の活用
障害年金を受給されている方が活用できる、税金に関する制度は他にもあります。
障害年金の特例について
繰り返しになりますが、障害年金が「非課税」であること自体が、税制上の大きな特例です。これにより、年金収入を気にすることなく、他の所得控除のメリットを最大限に活用することができます。
医療費控除の活用方法
病気やけがの治療で多くの医療費がかかった場合、医療費控除を確定申告で申請することで、税金の還付を受けられる可能性があります。これは、障害年金を受給している方ももちろん対象となります。年間の医療費の領収書は、必ず保管しておくようにしましょう。
給付金や他の制度との関係
障害のある方を支援するための経済的な給付は、障害年金以外にも様々あります。例えば、特別障害者手当なども非課税所得として扱われます。公的な給付を受ける際に、税金の心配をする必要はほとんどありません。
無料相談実施中
障害年金や税金の手続きは、専門用語も多く、一人で理解するのは難しいと感じられるかもしれません。しかし、正しく制度を知ることで、あなたの経済的な負担を軽くできる可能性があります。
「自分の場合はどうなんだろう?」
「手続きを手伝ってほしい」
もし、障害年金の申請そのものや、関連する手続きでお困りのことがありましたら、決して一人で悩まないでください。私たち障害年金の専門家は、いつでもあなたの味方です。
初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。
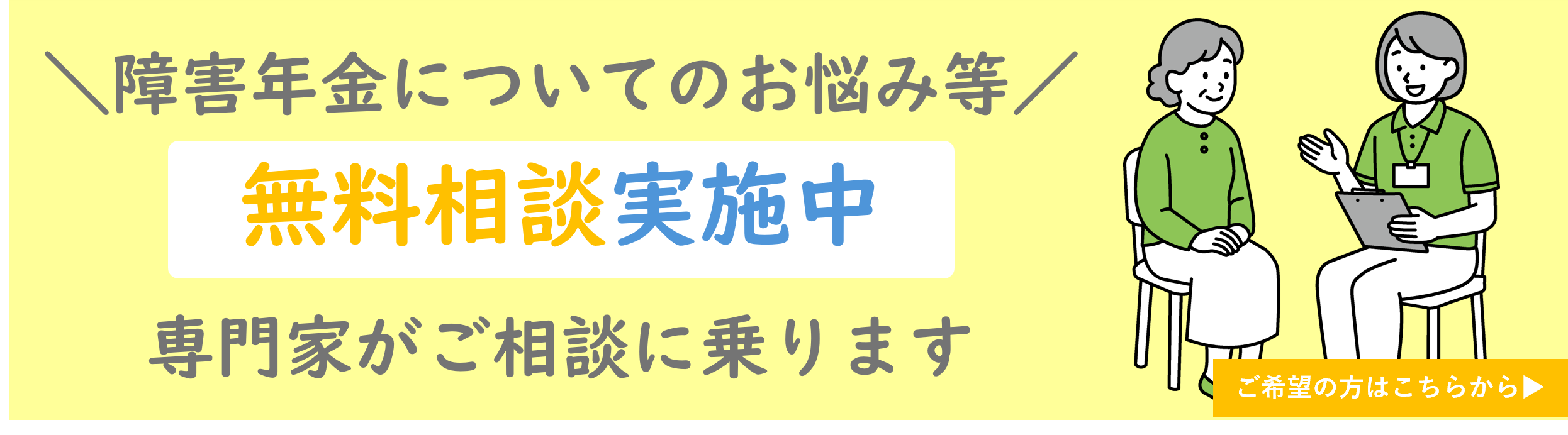
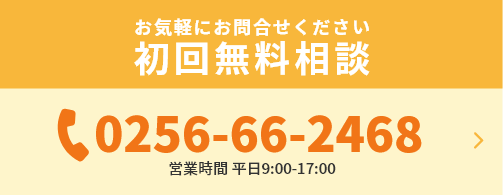
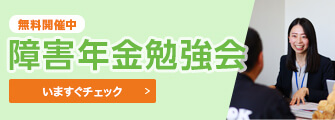
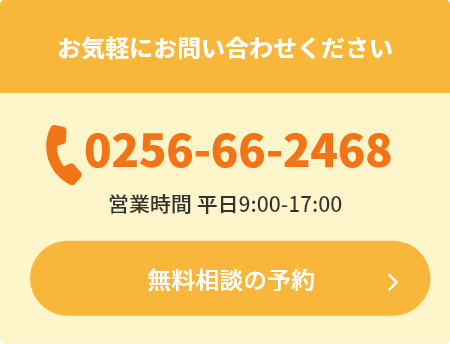
 初めての方へ
初めての方へ